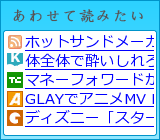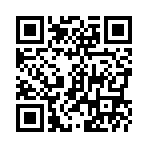トップページ>食べ物>土用は丑の日、うなぎの日
2007年07月30日
土用は丑の日、うなぎの日
今日は土用の丑の日ですね。
ただ、今年は中国産のうなぎの安全性が問題視されて、
うなぎの売り上げは減っているようです。
とはいえ、やっぱり今日は町のあちこちでうなぎを売っているところが見かけられました。
その“うなぎ”ですが、実はその生態系はよく知られていないそうです。
ウィキペディアによると、
(引用:ウィキペディア)
>ニホンウナギの産卵場所がグアム島沖のスルガ海山付近であることをほぼ突き止めた。
というように、うなぎは海で産まれるんですね。
私も知らなかったのですが、
“うなぎの養殖”といっても、
とのことで、シラスウナギから養殖しているのであって、産まれたところからではないのですね。
とのことで、最初からの養殖となるとなかなか難しいようです。
安全で安い国産うなぎを食べようと思うと、なかなかハードルが高いですね。
ただ、今年は中国産のうなぎの安全性が問題視されて、
うなぎの売り上げは減っているようです。
とはいえ、やっぱり今日は町のあちこちでうなぎを売っているところが見かけられました。
その“うなぎ”ですが、実はその生態系はよく知られていないそうです。
ウィキペディアによると、
ウナギは淡水魚として知られているが、海で産卵・孵化を行い、淡水にさかのぼってくる「降河回遊(こうかかいゆう)」という生活形態をとる。
従来ウナギの産卵場所はフィリピン海溝付近の海域とされたが、外洋域の深海ということもあり長年にわたる謎であった。しかし2006年2月、東京大学海洋研究所の塚本勝巳教授が、ニホンウナギの産卵場所がグアム島沖のスルガ海山付近であることをほぼ突き止めた。従来のウナギは冬に産卵説は誤りとされ、現在は6~7月の新月の日に一斉に産卵するという説が有力である。
卵から2~3日で孵化した仔魚はレプトケファルス(葉形幼生、Leptocephalus)と呼ばれ、親とは似つかない柳の葉のような形をしている。この体型はまだ遊泳力のない仔魚が、海流に乗って移動するための浮遊適応であると考えられている。レプトケファルスは成長して稚魚になる段階で変態を行い、扁平な体から円筒形の体へと形を変え「シラスウナギ」となる。シラスウナギは体型こそ成魚に近くなっているが体はほぼ透明で、全長もまだ5cm ほどしかない。
シラスウナギは黒潮に乗って生息域の東南アジア沿岸にたどり着き、川をさかのぼる。流れの激しいところは川岸に上陸し、水際を這ってさかのぼる。川で小動物を捕食して成長し、5 年から十数年ほどかけて成熟する。その後ウナギは川を下り、産卵場へと向かうが、その経路に関してはまだよく分かっていない。海に注ぐ河口付近に棲息するものは、淡水・汽水・海水に常時適応できるため、自由に行き来して生活するが、琵琶湖や猪苗代湖等の大型湖沼では、産卵期に降海するまで棲息湖沼と周辺の河川の淡水域のみで生活することが多い。また、近年の琵琶湖等、いくつかの湖沼では外洋へ注ぐ河川に堰が造られたり、大規模な河川改修によって外洋とを往来できなくなり、湖内のウナギが激減したため、稚魚の放流が行われている。
(引用:ウィキペディア)
>ニホンウナギの産卵場所がグアム島沖のスルガ海山付近であることをほぼ突き止めた。
というように、うなぎは海で産まれるんですね。
私も知らなかったのですが、
“うなぎの養殖”といっても、
ウナギの養殖はまず、天然のシラスウナギを捕ることから始まる。黒潮に乗って日本沿岸にたどり着いたウナギの子ども、シラスウナギを大量に漁獲してこれを育てるのである。
とのことで、シラスウナギから養殖しているのであって、産まれたところからではないのですね。
なお、ウナギの人工孵化は1973年に北海道大学において初めて成功し、2003年には三重県の水産総合研究センター養殖研究所が完全養殖に世界で初めて成功したと発表した。しかし人工孵化と孵化直後養殖技術はいまだ莫大な費用がかかり成功率も低いため研究中で、養殖種苗となるシラスウナギを海岸で捕獲し、成魚になるまで養殖する方法しか商業的には実現していない。
とのことで、最初からの養殖となるとなかなか難しいようです。
安全で安い国産うなぎを食べようと思うと、なかなかハードルが高いですね。
Posted by 青い夜 at 19:04│Comments(0)
│食べ物